この記事では米、特に玄米の栄養価の優れた点や美味しい食べ方を解説しています。味と安全性どちらも優れた発芽玄米として発芽玄米を実体験をもとに食と健康のプロがご紹介します。
日本と同じアジア圏のインドではデルタ地帯や南部で米食は大変盛んで、インドにも玄米文化はあり、バスマティ玄米が売られています。日本では白米が主流ですが、従来は玄米が当たり前のように庶民の食卓にのぼりました。
西暦1600年頃に脱穀機が生まれ、効率的に白米を作れるようになりましたが、それでも当時は貴重な食材でしたので、庶民生活では玄米や雑穀が流通の中心でした。
糖尿病と癌が戦後に急増した理由とは?

戦後の日本では洋食が主流になりました。大量の植物油の消費が始まり、家庭ではフライパンでホットケーキやハンバーグなどを作るようになり、外食ではお惣菜、特に唐揚げやコロッケなどの揚げ物が売れる時代になりました。学校給食ではパンが主食として登場して以来、小麦食文化が定着しました。その結果、糖尿病は30〜50倍、癌患者は4倍に増えました。
自動車の普及など近代化による運動不足が原因と言われていますが、根本原因は食事による「食源病」です。
人は民族ごとに遺伝子が異なります。各々腸内細菌は異なり、消化酵素も異なります。たとえば、海苔を分解できるのは日本人と韓国人だけと言われています。
ヨーロッパを中心とする白人種は小麦のグルテン蛋白の毒性に耐性を持ちます。また、北極圏に暮らすイヌイットやエスキモーはアザラシの生肉を消化できます。
ハワイの日系人の病気を3世代追跡したところ、現地の食事を続ける中で本来の日本人には起きなかった病気が増えました。こういった劇的な食生活の変化に人間は適応できません。遺伝子レベルで体が対応するには8000年かかると言われています。
病気にならないためには?

食の見直しは日本人にあった食の原点回帰の旅の出発点といえます。糖尿病や癌といった急激に増えた病気は第二次世界大戦後の劇的な食の変化が発端です。なので、それ以前からご先祖が食していた食事に戻してあげることが健康への近道となります。このブログでは次の対策を提案します。
- 植物油を取り過ぎない(トランス脂肪酸を避ける事も)
- 精白した炭水化物を避ける
- 小麦全般を避ける
1の油については過去記事を参考にしてみてください。おすすめの油や米についてもご紹介しています。
2については以下の過去記事が参考になります。
小麦については別記事で詳しくご紹介しますが、日本の食文化である米食への回帰は、第一次産業を守ることにもつながります。
糖尿病は遺伝の影響が非常に大きい病気です。遺伝的に不利な体質の方は、この記事でご紹介するような万人に合った一律の方法では健康につながらないこともあります。その場合は、糖質制限などご自身に合った方法を模索していくことが必要です。
粗食こそ健康への近道
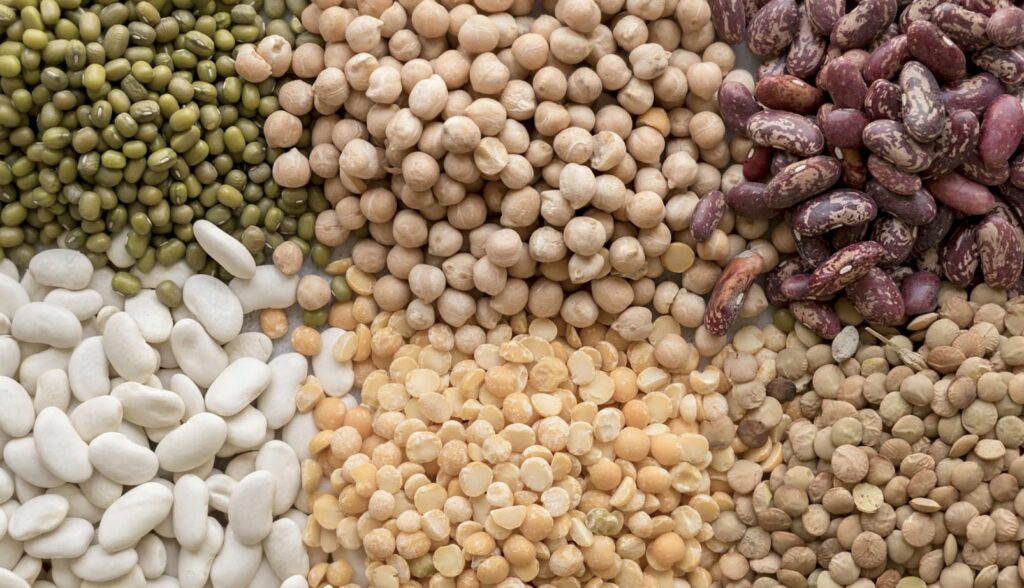
粗食イコール貧しい食事ではありませんし、断食でもありません。病気にならない安全な食材を自ら選び、しっかり摂る。これが現代で実践すべき粗食です。
この粗食を支えるものとして注目されているのが雑穀です。雑穀とはなんでしょうか?雑穀についての定義はウイキペディアでは次のように記載されています。
雑穀(ざっこく)(英: millet)とは、主穀ではない穀類の総称[1][2]。生物学的分類ではなく農学的分類である。日本では「主穀」は基本的に米を指すが麦を含めることも多いとされ[1]、一般に米・小麦・大麦を除く穀類及び擬似穀類を「雑穀」とするが[3]、一方で「雑穀」に豆類を含めるかどうかについて分かれるなど曖昧さをもつ概念である[1]。ただ、いずれも小規模に作付けされ、世界中で食糧や飼料として広く栽培されている作物である。それらの本質的な類似点は、生産性が低い環境に育つ小規模に作付けされた草本ということである。中国の新石器時代や韓国の無文土器時代など、原始的な社会の食生活においては、米よりもむしろ雑穀が重要部分を構成していた。
WIkipediaより
健康を根本から考え直すと結局のところ可能な限り手をつけていない食品に戻っていきます。つまり粗食、米や雑穀を中心とした暮らしの立て直しです。
たとえば豆腐や味噌の原料は大豆であり雑穀の一種です。米は雑穀ではないですが、米と一緒に雑穀を炊いて麦飯や小豆ご飯などにすることができます。
玄米の栄養価がすごい

粗食で一番オススメなのが、玄米です。一方で今の流通の主流は白米です。こちらはGIが高く血糖スパイク(血糖値の急上昇)を発生させやすい食べ物です。甘味が強く人気があります。
もちろん、白米を他のおかずと一緒に食べる事である程度は防ぐことは出来ますが、糖耐性の低い私のような方にはやはり不向きです。そこでこの記事では玄米をオススメします。
玄米は栄養価も優れ、精米の過程で削り落とされる部分(殻、胚芽、ぬかといった部分)にビタミンB群、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル、食物繊維、タンパク質をたくさん含む点もおすすめの理由です。ただし、殻、胚芽、ぬかといった部分は農薬の影響を受けやすいのが問題。減農薬、できれば無農薬が望ましいですね。
発芽玄米とは?
発芽玄米とは玄米を発芽させる事で栄養価を高めた玄米のことです。ご自身で発芽させることもできるのですが、酵素の力で発芽させ、乾燥させ、パック詰めしたものが発芽玄米として売られています。
筆者は食と健康の重要性を感じている一人です。インド料理の探求の結果、スパイスという健康のキーワードがありました。それは伝統に基づくものでした。
日本ではどうでしょうか?
同じく日本の食を遡っていくと玄米に出会いました。
健康を見据えた安心安全の玄米

味と安全性を両方兼ね備えたものを厳選した結果、この発芽玄米に辿り着きました。まず、国内材料100%、残留農薬ゼロ、保存料不使用という点に惹かれ試しに購入しました。
購入して届いた箱の中にお礼の紙が入っていて、それを読んでみると誠実な商売の姿勢にも惹かれてしまいました。先代は当初飲食店をされていたそうですが、色々と経緯があり、妥協できない姿勢があったようで安心安全な食を提供したい思いから、米を自分たちで作る事にしたそうです。この正直な姿勢にも共感しました。
健康を追求していくと、レトルトや電子レンジに不信感を持つ方もいます。これには賛否両論あります。携帯電話の電波がいたる所にある中を生き、万が一にもパック寿司やお弁当を食べるなら議論の余地はありません。健康に100点を目指す気持ちは同じですが100点で生きれるほど現代は甘くありません。もし避難生活を余儀なくする場合、食に選択肢はないのですから。
原料へのこだわり

この発芽玄米は九州山脈の地下水で定期的に水を換えながら24時間かけて発芽しています。
原料は、全て国産にこだわった大分県産のうるち米、小豆は北海道産、塩は大分県産のものを使用しています。さらに、この玄米は発芽させる事で以下のように栄養素が増加し、炊飯後に三日寝かせることで甘みや食感も向上することがわかっています。
米は残留農薬がゼロとなっています。安心安全ですね。
白米と比較して鉄分、カルシウム、カリウムは4倍、ビタミンB1とビタミンEは4.5倍、食物繊維は9.5倍、マグネシウムは12倍も含まれています。
玄米を炊飯するにはどうすればいい?

以下の手順で美味しく熟成させるのがポイントです。(熟成しなくても食べれます。)
1)浸水
炊飯器で1時間浸水する。必ずミネラルウォーターを使います。玄米モードがある電気炊飯器をお持ちの方はそれに水分量を合わせれば完璧で、白米モードしかない場合は白米のラインまで水を入れてさらに計量カップで一合あたり50cc、少し多めに1カップ入れれば上手く炊けます。玄米は吸収が悪いので白米よりは多めに水を入れてあげないと硬い仕上がりとなります。
2)炊飯
私の場合は、ガスコンロの炊飯モードで炊いてみました。炊飯後そのまま食べることも出来ますが、次の工程を踏むとさらに美味しくなります。
3)熟成
3日間73度で保温し、毎日一回攪拌することでモチモチの仕上がりとなります。(三日後、冷凍保存も可能です。)
保温用に炊飯器を用意する
筆者はガスコンロで炊飯します。そこでガス炊飯後に玄米を寝かせる方法がありませんでした。そのために、口コミなどを頼りに半年間探し抜いて、ようやくたどり着いたのがタイガーの保温専用ジャーです。
この家庭用の保温専用ジャーはタイガーという歴史が裏付けるように安心できる炊飯器メーカーでありながら、とんでもなく安い部類に入ります。かわいい花柄の見た目がレトロで昭和を感じさせる点も何か日本人には懐かしさを感じてしまいます。(笑)
ご家庭で使う場合は、6合タイプが一番おすすめです。3合(または2回炊いて6合)を炊いて一升を超える大きいジャーで保温しても水分量や熱量などを考えると大は小を兼ねません。6合が家庭用ではちょうど良いサイズだと思います。
価格で見ると業務用の保温ジャーは値段が高いのが欠点ですし、安い中華製の炊飯器はご飯が乾燥しやすいという口コミが非常に多いのが現実です。米が変色してしまったという意見も多く、温度管理なのかフタの設計があまり良くないように感じました。
間違った保温でせっかく炊いたお米の質を下げては、安物買いの銭失いになりかねません。そこでタイガーの保温ジャーに決めました。
炊飯する余裕がない時もある

実は、もう一つの玄米に出会いました。もっちもちの玄米革命!結わえるの寝かせ玄米ごはんパックという商品です。これは備蓄用玄米を探していたときに見つけました。
色々調べてみると、こちらの社風も気に入りました。現代的な暮らしの中で忘れられつつある伝統的な食文化の見直しがあるべきだという考え方に共感できました。無添加をモットーにされている点も見逃せませんね。
災害備蓄のローリングストックを兼ねて何回か購入しました。黒米や小豆、もち麦、15穀の四種類のセットで、食べ比べできます。玄米の寝かせ具合がよく、噛んだときに適度のもちもち感があり、玄米特有のパサパサ感は全くありませんが、温め具合が悪いと米が固まったままになる時がありました。
レトルトの封をあまり開けずに電子レンジにかけると圧力が上がって熱の通りが良いことに気づきました。
ところで、健康を考えるのはもちろんですが、皆さんは
まとめ
食と健康の意識が非常に高まっている今こそ健康を取り戻す、日本人らしい正しい食生活への回帰という点から「粗食」をオススメし、玄米をご紹介しました。玄米を色々と探し回った結果、発芽玄米という栄養が優れたものに出会いました。中でも味と安全性のどちらも優れた発芽玄米をご紹介しました。
次回の記事では、食と健康のプロが安全な雑穀をご紹介します。









コメント